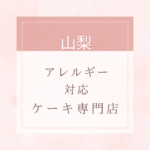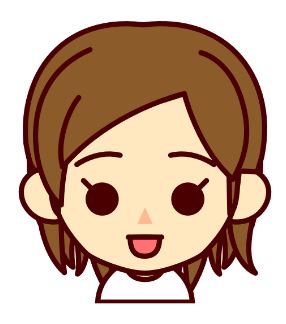※このページはPRを含みます。
「またこれしか食べないの?」「どうしてうちの子は…」
そう悩む親御さんの中には、「子供の偏食は親のせいかもしれない」と自分を責めてしまう方も少なくありません。
でも実際には、偏食には成長段階や体質、感覚特性など多くの要因が関係しており、親だけが原因ではありません。
この記事では、偏食を無理に矯正するのではなく、“子どもに合った食の関わり方”を学ぶ方法をご紹介します。
✅この記事を読むことでわかること
・子どもの偏食に“親のせい”という決めつけが危険な理由
・偏食の背景にある“感覚・発達・環境”の要因
・無理せず、少しずつ“食の幅”を広げていくアプローチ方法

目次
子どもの偏食は“親のせい”ではなく“理解不足”かもしれない
偏食が続くと「甘やかしすぎた?」「ちゃんと育てられてない?」と悩む親御さんも多いですが、実は“親のせい”ではなく、食べ物への感覚過敏や心の発達段階が影響している場合が多くあります。
その背景にある“子ども特有の理由”を、しっかり知ることがスタートです。
子供 偏食 甘やかしと誤解されるケース
「好きなものばかり与えていたかも…」
そんな風に過去を振り返って、自分を責めてしまう親御さんは少なくありません。
ですが実際には、子どもの偏食は“甘やかし”とは限らないのです。
偏食の背景には、味覚や食感への敏感さ・消化機能の未熟さ・ストレス反応や心理的要因が複雑に絡んでいることもあります。
だからこそ必要なのは、「ダメな親だった」と思うことではなく、
子どもの偏食の理由を理解し、寄り添う姿勢を持つこと。
講座では、家庭でできる無理のない対応や、子どもと向き合うコミュニケーションのコツが学べます。
無理なく家庭でできる“正しい対応”を学ぶならこちら
↓食育栄養アドバイザー講座を見る↓
![]()
子供 偏食 発達障害との関連を知る
偏食が極端で、「決まったものしか食べられない」「見た目が少しでも違うと口にしない」など、強いこだわりがある場合には、発達特性(自閉スペクトラム症など)との関わりがあることも。
こうしたケースでは、感覚過敏やルーティンを好む傾向が影響している可能性があります。
「なんで食べないの?」と叱るよりも、その子にとっての“安心できる食”とは何かを探ることが大切です。
講座では、発達への理解を含めた“食との関わり方”を学び、「無理に食べさせる」のではなく「その子に合ったアプローチ」が見えてきます。
食と発達をつなぐ家庭の理解を深めるなら
↓栄養と感覚特性を学べる講座はこちら↓
![]()
子供 偏食 疲れた…頑張る親ほど陥る消耗
「今日も食べてくれなかった…」「何を作っても無駄かも」
そんな思いが積もって、食事の時間がつらくなる親御さんは本当に多いです。
とくに、毎日毎日がんばっている親ほど、「こんなに頑張ってるのに…」という気持ちがつらさに変わってしまうことも。
でも、まず大切なのは、“親自身がラクになる視点”を持つこと。
講座では、子どもへのアプローチ方法だけでなく、親のメンタルケアや食事への負担を減らす工夫まで学ぶことができます。
「自分が悪いんじゃないか」と悩む前に、少し立ち止まって、
“親自身が元気でいられる食育”を取り入れてみませんか?
親の心を守る食育を知りたい方はこちら
↓食事のストレスを減らすヒント↓
![]()
偏食の“背景”を知れば、対応のしかたが変わる
偏食があると、つい「好き嫌いが多い=困った性格」と思ってしまいがちですが、
子どもにとっては“防衛反応”である場合も多いのです。
そのためには、“ただ食べさせる”のではなく、なぜ偏食なのか?に向き合う姿勢が大切です。
ここでは、その具体例を紹介します。
同じものしか食べない子供に見られる傾向とは?
「決まったものしか食べない 小学生」
「同じものしか食べない 発達障害」
このような検索が多い背景には、“うちの子だけ?”という不安が多くの親に共通しているからです。
ですが、特定の食べ物ばかりを好むのは、子どもにとって“安心の証”であることも。
味・食感・見た目に安心感を持てるものに頼ることで、未知のものへの不安をやわらげているのです。
講座では、このような「偏った食の背景にある心の状態」も大切に考え、
子どもの心と体、どちらにも配慮した対応方法が学べます。
👉 子どもの“こだわり食”と向き合うヒントはこちら
家庭で実践できるアプローチを学ぶ
子供 偏食 ひどい場合のステップ対応
「全然食べてくれない」「野菜を見るだけで泣く…」
そうした“偏食がひどい”ケースでは、無理やり食べさせるよりも“慣れるステップ”が大切です。
まずは見せるだけ、触れるだけ、ひと口だけ──
小さな成功体験を積み重ねることで、苦手が少しずつ“怖くない”に変わっていきます。
講座では、そうした段階的な進め方や、「こんな声かけでよかったんだ」と親自身が安心できる工夫も学ぶことができます。
子どもが“食べる力”を育てるステップとは?
↓講座で学べる実践知識はこちら↓
![]()
好き嫌いが多い子供 原因を親が知っておく意味
「どうしてこんなに好き嫌いが多いんだろう」
「作っても食べてもらえないと、もうつらい…」
そう感じるときこそ、“苦手な理由”に目を向けることが偏食改善の第一歩です。
子どもは、うまく言葉にできないけれど、「においがイヤ」「口の中でぐにゃっとするのが苦手」など、理由がちゃんとあることも少なくありません。
親がその“見えない理由”に気づけるようになると、「これは受け入れられるかも」といった工夫の糸口が見えてきます。
講座では、そんな子どもたちの感覚や心理に寄り添った対応が学べます。
食の“見えない理由”に気づけるようになりたい方へ
↓家庭でできる“原因アプローチ型”の食育はこちら↓
![]()
まとめ:偏食と向き合うために必要なのは“知識”と“安心感”
子どもの偏食は、決して「親のせい」ではありません。
その子の体質・感覚・成長段階に合わせた対応が必要であり、正しい知識と余裕を持って関われるかがカギです。
【食育栄養アドバイザー講座】では、偏食や好き嫌いと向き合う実践的な知識に加え、
親自身の心のケアや接し方までしっかり学べます。
✅「食べさせなきゃ」に疲れた方
✅「この子の偏食、どう向き合えば?」と感じている方
そんな親御さんこそ、一度“学びの時間”を取ってみませんか?