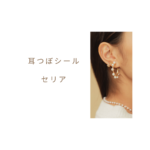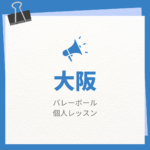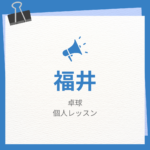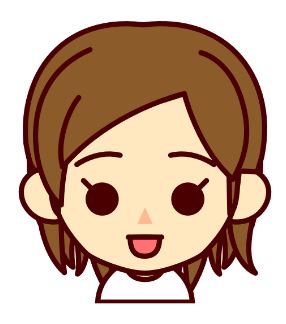※このページはPRを含みます。
「喪中なのにおせちを買ってしまった…」
そんな時、食べてもいいのか、返品すべきなのかと迷う方も多いのではないでしょうか。
実は、喪中でも宗派や考え方によって対応が異なります。
この記事では、喪中におせちを買ってしまったときの正しい対処法や、代わりの「ふせち料理」について分かりやすく解説します。
| 特徴 | 無添加・自然派食材中心。野菜たっぷりで健康志向。 |
|---|---|
| 味・見た目 | やさしい味、彩り控えめでナチュラル。 |
| 安心感 | 国産素材&自社製造で安全 |
| 特徴 | 料亭監修おせちの通販大手。顧客満足度94%以上。 |
|---|---|
| 味・見た目 | 華やかで豪華、家族向け。 |
| 安心感 | 有名料亭監修で信頼性抜群 |
| 特徴 | 創業55年の老舗。添加物不使用の冷凍惣菜で有名。 |
|---|---|
| 味・見た目 | 上品な味わい、冷凍でも高品質。 |
| 安心感 | 徹底した安全基準で安心 |
✅この記事を読むことで分かること
・喪中におせちを食べてもいいか?宗派ごとの考え方
・「ふせち料理」とは?おせちの代わりになる料理の意味
・高島屋・イオンなどの「喪中対応おせち」情報

目次
喪中におせちを買ってしまった…どうするのが正解?
喪中におせちを買ってしまった場合、「食べるのは非常識なの?」「お正月料理は控えるべき?」と不安に思う方が多いです。
ですが、実際は喪中でもおせちを食べること自体に問題はないケースがほとんど。
ここでは宗派別の考え方と、心を込めた過ごし方のヒントを紹介します。
喪中でもおせちを食べていい?基本の考え方
喪中は「お祝い事を控える期間」と言われていますが、だからといって必ずしも「おせちはNG」というわけではありません。
そもそもおせちは、新しい年の無病息災・五穀豊穣・家族の健康と長寿を願うための料理です。
つまり、「お祝い」だけでなく「感謝」や「祈り」の意味も込められているんです。
そのため、喪中でも「おせちを食べること=マナー違反」にはなりません。
大切なのは、どんな気持ちで新年を迎えるかという点。
故人を思いながら、静かに感謝の気持ちを込めて食卓を囲むなら、十分に礼を尽くした新年の迎え方といえるでしょう。
たとえば、こんな工夫をしてみると良いですよ。
-
お重箱ではなく、白いお皿に一人ずつ盛り付ける
-
紅白かまぼこや伊達巻など「お祝い色の強い食材」を控える
-
祝い箸ではなく、普段使いのお箸を使う
-
「今年も家族そろって健康でいられますように」と、
ひとこと故人に心の中で報告してから食べる
こうして見ると、「喪中だからおせちを食べられない」というよりも、「祝い方を変える」という考え方がしっくりきますね。
食卓の雰囲気を落ち着かせるだけで、ぐっと気持ちも穏やかになります。
宗派による違い|浄土真宗と曹洞宗の考え方
喪中におせちを食べても良いかどうかは、宗派の考え方にも少し違いがあります。
ここでは、代表的な「浄土真宗」と「曹洞宗」の考えをわかりやすく紹介します。
【浄土真宗の場合】「死は穢れではない」からおせちは問題なし
「喪中 おせち 浄土真宗」で調べる方も多いように、浄土真宗の教えは他宗派と少し異なります。
浄土真宗では、「死=穢れ(けがれ)」としないという考え方が基本です。
亡くなった方は“仏となって浄土へ往生される”とされており、悲しみの中にも「ありがたさ」や「感謝」の心を重んじます。
そのため、おせち料理を避ける必要はまったくありません。
ただし、「祝いごとを派手に行う」というよりも、心静かに感謝の気持ちを持って新年を迎えることが大切です。
たとえば、こんな過ごし方が理想的です。
-
おせちはそのままでも構わないけれど、華やかすぎない盛り付けを意識する
-
家族で集まる際は、「今年も仏様に見守られて迎えられたね」と感謝を伝える
-
正月飾りや門松など“お祝い色の強いもの”は控える
こうした工夫をすることで、「形式的に避ける」のではなく、心の持ち方を整えるお正月にすることができます。
【曹洞宗の場合】故人への感謝を込めて食事をいただく
次に、「喪中 おせち 曹洞宗」の場合を見てみましょう。
曹洞宗は、日々の暮らしの中に“修行”があるという考え方を大切にします。
ですから、食事をすることも仏道の一つとされています。
おせちを食べるかどうかに厳しい決まりはありません。
むしろ、故人に感謝しながら、静かにおせちをいただくことで、「今、生かされていることに感謝する」気持ちを深めることができます。
曹洞宗ではこんな習慣を取り入れる家庭もあります。
-
食事の前に、仏壇に一膳をお供えする
-
「いただきます」の前に、亡き人を思い出して心の中で感謝する
-
おせちは、落ち着いた色味のものを中心に構成する
たとえば、黒豆や数の子の代わりに、里芋の煮物や昆布巻き、白かまぼこを中心にすると上品な印象に。
“華やかさ”よりも“心を込めて作ること”を大切にすれば、喪中であっても立派な新年の食卓になります。
喪中でも食べられる「ふせち料理」とは?静かに新年を迎えるための食の形
喪中の新年は「祝い事を控えながらも、家族の健康を願う」期間です。
そのため、おせちを“やめる”のではなく、“落ち着いた形で取り入れる”という選択をする人が増えています。
ここでは、喪中でも心をこめて食卓を囲むための具体的な選択肢を紹介します。
ふせち料理の由来と特徴
実はこの「ふせち料理」、歴史はとても古く、平安時代の宮中行事が起源といわれています。
当時は「季節の節目に災いを避ける食事」として親しまれ、“避ける”という意味から「伏せち(ふせち)」と呼ばれるようになりました。
現代のふせち料理は、華やかさを抑えた控えめで心落ち着く料理構成が特徴です。
たとえばこんなメニューが定番です。
-
昆布巻き:喜び(よろこぶ)に通じるが、落ち着いた色味で控えめ
-
煮しめ:家族が仲良く結ばれる願いを込めて
-
白かまぼこ:紅白のうち白のみを使用し、清らかさを表す
-
里芋や人参の炊き合わせ:素朴で優しい味が喪中の心に寄り添う
味つけも濃すぎず、見た目も華やかすぎないため、「静かに新年を迎える」という心にぴったり寄り添う料理です。
ふせち料理は「食を抜かずに心を整える」料理
「喪中だからおせちをやめる」ではなく、「喪中だからこそ感謝の食卓を囲む」——。
そんな想いを形にしたのが、ふせち料理の考え方です。
喪中は悲しみの期間ですが、家族の健康や平穏を願う心は変わりません。
むしろ、「静かに、感謝していただく」という姿勢こそ、新しい一年を迎える上で大切な祈りの形です。
最近では、デパートやスーパーでも「ふせち料理 高島屋」や「ふせち料理 イオン」など、
喪中向けのおせちを取り扱う店舗が増えています。
華やかさを抑えた色合いと上品な味わいが人気で、年末の定番になりつつあります。
高島屋の「ふせち料理」・喪中おせち
「ふせち料理 高島屋」や「喪中 おせち(高島屋)」で検索されるように、高島屋では毎年、お祝いを控えたい方向けの落ち着いたおせちを用意しています。
紅白の色味を抑え、昆布巻き・煮しめ・野菜の炊き合わせを中心とした構成で、見た目にも穏やかで、心静かに新年を迎えられると好評。
また、包装やパンフレットのデザインもシンプルで、贈答用としても失礼のない上品さが魅力です。
「華やかではないのに美味しい」「優しい味が心にしみる」という口コミも多く見られます。
イオンの「ふせち料理」・喪中向けおせち
「ふせち料理 イオン」でも検索されるように、イオンでも喪中でも楽しめる落ち着いたおせちシリーズを展開しています。
華やかすぎず、素材を生かしたやさしい味付けが特徴で、「お祝いではなく“感謝の膳”としていただける」と評判です。
ネット注文にも対応しており、冷凍配送で年末に余裕を持って準備できるのも嬉しいポイント。
「喪中でも気持ちが安らぐ」「家族で穏やかに過ごせた」とリピート購入する方も多いようです。
まとめ|喪中でも「心を込めて食を大切にする」ことが一番大事
喪中におせちを買ってしまっても、非常識ではありません。
宗派や家庭の考え方によって違いはありますが、大切なのは「静かに感謝して新年を迎える心」です。
華やかなお祝いを控えたい場合は、「ふせち料理」や「落ち着いた喪中おせち(高島屋・イオン)」を選ぶのがおすすめ。
形式にとらわれすぎず、“家族の絆と心の温かさ”を感じる時間を大切に過ごしたいですね。
ここでは、マナーを守りながら新年を穏やかに迎えるためのヒントを紹介しました。