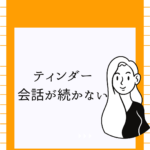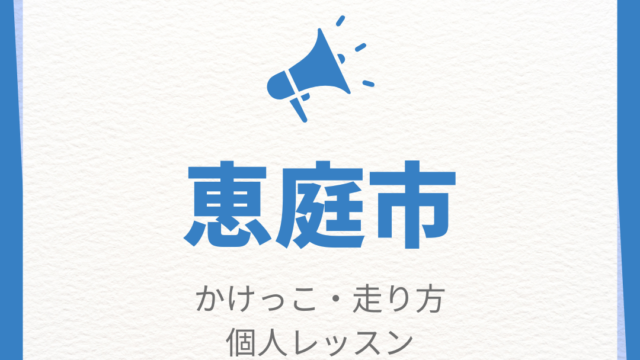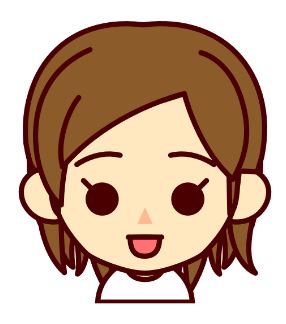※このページはPRを含みます。
「療育 辞めたい」と思うことは、親としても子どもとしても自然なことです。
「遊んでるだけ」「健常児だった?」「本当に続ける意味があるの?」
そんな迷いがある方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、療育を辞めた/辞めてよかったという声から、辞める判断のヒントと辞めた後に役立つ家庭でのサポート法+学び直し講座をご紹介します。
↓療育を続けるか迷う親御さんにおすすめ!四谷学院通信講座はこちら↓
✅この記事を読むことでわかること
・療育を辞める親のリアルな声:「辞めてよかった」って本当?
・辞める手続きやタイミング、止めさせてくれないケースの対処法
・辞めた後悔や悪影響の声にどう向き合うか
・その後の“家庭療育力”を伸ばす学び方とサポート方法
・親が学ぶ療育通信講座を活用して、安心して辞められる準備

目次
療育を「辞めたい」と思うことは当たり前──無理なく判断するヒント
療育に通い始めて数ヶ月、子どもが 「遊んでるだけに見える」、本人が「行きたくない」と言い出すこともあります。
また、「療育 健常児だったのでは?」と不安になる親御さんも少なくありません。
こうした気持ちは決して珍しいものではなく、療育の効果や必要性を見直すタイミングが来ているサインかもしれません。
大切なのは、単に「辞めたい」という感情だけで判断せず、実際に療育を辞めた親御さんたちの声を聞きながら、子どもにとって最適な選択が何かを冷静に考えることです。
次に、実際に療育を辞めて良かったと感じた人の声や、辞めたことで後悔したケースも紹介します。判断の参考にしてください。
辞めてよかったという声・辞めた後悔の理由とは?
「辞めてよかった」と感じる親御さんの声
-
「子どもが笑顔で過ごす時間が増え、家族全体が穏やかになった」
-
「療育にかけていた時間や労力を、家族の他の活動に充てられるようになった」
-
「本人のペースに合った支援方法を見つけられた」
こうした声からは、無理に続けるよりも子どもの心身の安定を優先した結果、良い変化が生まれたことがわかります。
一方で、辞めたことで後悔したケースも
-
「療育に通わなかったために集団生活の基本スキルが不足し、学校生活で困ることが増えた」
-
「療育機関のサポートを受ける機会を逃してしまい、必要なサービスが受けられなくなった」
-
「途中でやめてしまったため、再度利用したい時に手続きや受け入れが難しかった」
辞めた後悔は、継続した療育が必要だったのに本人や親が判断を誤ったケースや、制度の理解不足によることも多いです。
判断のポイント
「遊んでるだけ」に見えても、療育の場では本人が無意識に学んでいることも多くあります。
だからこそ、「今の状況で療育が必要かどうか」「子どもの成長段階や性格に合っているか」「家庭や学校との連携が取れているか」など、総合的に見直すことが大切です。
そして、「辞める」か「続ける」かではなく、「どうすれば子どものためになるか」を考えることが最も重要。
療育の判断や支援方法に迷った時は、親がしっかり学び直すことが大切です。
【四谷学院の療育・発達支援通信講座】なら、スキマ時間に無理なく学べ、療育の基礎知識から家庭でできる支援法までしっかり身につきます。
↓療育を続けるか迷う親御さんにおすすめ!四谷学院通信講座はこちら↓
![]()
辞めるための手続き・止めさせてくれない時の対処法
療育施設によっては、辞めたい意思を伝えても簡単に辞められないケースもあります。
また、「遊んでるだけなのに通ってて本当に必要?」と感じることも。
辞める正式手続きと円満退所のコツ
-
行政や医療機関では、退所申請書の提出が必要なケースあり
-
民間施設は契約書に基づく解約規定の確認が重要(1ヶ月前通知など)
-
担当者との面談を設け、「これからどうしていきたいか」を共有することで、円満退所につながります
「辞めさせてくれない」施設への対応法
-
行政が関わっている場合は、担当部署や相談窓口に相談
-
医師・支援者と家庭の現状や子どもの希望を共有し、減回数や週1通所など調整を検討
-
施設を変える・別支援に切り替える選択も視野に。親の判断を後押ししてくれる相談相手を見つけることが大切です
家庭で育める“生活支援力”──辞めた後のサポート方法
辞めた後も子どもの自己肯定感やコミュニケーション力を育てる方法は多くあります。
日常の中でできる「療育ごっこ」を取り入れる
-
お片付けルールや「できたね!」という声かけで習慣づくり
-
生活リズム表・時間管理・温かい共感的コミュニケーションで家庭療育力を高める
-
再度不安が強くなる時期があれば、勉強会参加や相談を活用できます
↓療育を続けるか迷う親御さんにおすすめ!四谷学院通信講座はこちら↓
親が学ぶ・資格を取ることで、辞めた後も安心できる選択肢に
療育を辞めたいと思っても、「知識がないまま1人で頑張るのは不安」という声は多いです。
だからこそ、家庭療育力を高める学びや資格取得は、安心につながります。
通信講座で「療育力+自信」を育てる方法
療育を「辞めたけど、これからも子どもを支えたい」「療育の知識をもっと深めたい」という親御さんに、通信講座は非常に効果的な学びの手段です。
スキマ時間で無理なく学べる
忙しい毎日の中でも、スマホやパソコンを使って好きな時間に学習できます。
通学の必要がなく、自宅で自分のペースで進められるため、仕事や家事、他の子育てと両立しやすいのが大きな魅力です。
臨床心理や発達支援の専門知識が身につく
通信講座では、発達障害の理解や子どもの行動分析、効果的な支援方法について体系的に学べます。
専門家が監修したカリキュラムで、正しい情報を基にした支援力が自然とアップします。
親子への具体的な関わり方や生活スキル支援法を学べる
単なる知識だけでなく、日常生活で実践しやすい療育のコツや声かけの方法、自己肯定感を育てる会話術などが充実。
親自身が自信を持って子どもに接し、無理なく継続できる内容が特徴です。
親がしっかり学ぶことで、子どもも安心して成長できる
療育の現場に頼りきりにならず、家庭での支え方を学ぶことは子どもの安心感につながり、長期的な成長を支えます。
また、知識とスキルが身につくことで、親自身のストレスも軽減されるため、家族全体の幸福感もアップします。
【四谷学院通信講座《療育・発達支援コース》】は、親御さんが無理なく学べる充実した内容とサポート体制が評判です。
療育の悩みを持つ方や、これから療育を辞める・変える判断を考えている方にもおすすめです。
まとめ|療育を辞めたいその気持ちを大切に
-
「辞めたい」は自然な気持ち、自分にも子どもにも優しくてOK
-
判断は「辞める」「続ける」ではなく「今の必要に応じて決める」視点で
-
手続きや施設変更、家庭での支援準備が次の安心につながります
-
親が知識とスキルを身につければ、より安心して辞める/再スタートすることができます
✨ 親子にとって、本当に必要な支援・学びのタイミングを自分たちで決めていきましょう。
↓ 四谷学院の通信講座で、安心して辞められる準備を始めませんか?↓
![]()