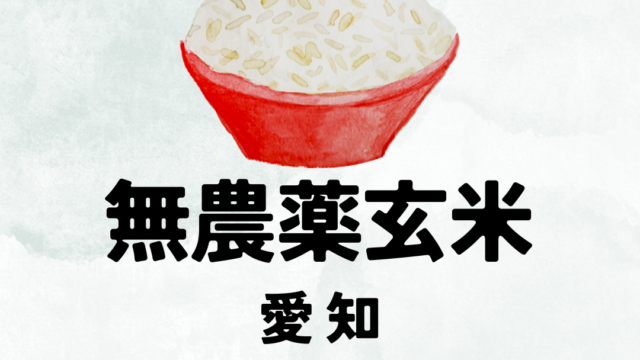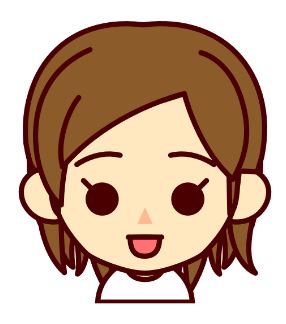※このページはPRを含みます。
お正月といえば「おせち料理」。
でも、「おせちは何日前から作るの?」「いつまで日持ちするの?」と悩む方も多いですよね。
この記事では、おせちを作るタイミング・日持ちの理由・手作りを安く仕上げるコツまで詳しく紹介します。
| 特徴 | 無添加・自然派食材中心。野菜たっぷりで健康志向。 |
|---|---|
| 味・見た目 | やさしい味、彩り控えめでナチュラル。 |
| 安心感 | 国産素材&自社製造で安全 |
| 特徴 | 料亭監修おせちの通販大手。顧客満足度94%以上。 |
|---|---|
| 味・見た目 | 華やかで豪華、家族向け。 |
| 安心感 | 有名料亭監修で信頼性抜群 |
| 特徴 | 創業55年の老舗。添加物不使用の冷凍惣菜で有名。 |
|---|---|
| 味・見た目 | 上品な味わい、冷凍でも高品質。 |
| 安心感 | 徹底した安全基準で安心 |
✅この記事を読むことでわかること
・おせちは「何日前から」作るのが理想か
・日持ちする理由と、作り置きのコツ
・定番おせちと手作りを安く・おしゃれに仕上げる方法

おせちは何日前から作る?作る順番と保存のポイント
おせちは本来、“年神様を迎えるための準備料理”であり、年末のうちに仕込みを終えるのが伝統です。
ここでは、おせちは何日前から作るのがベストか、何から作ると失敗しないかを具体的に紹介します。
おせちは「3日前」から作り始めるのが理想
「おせちは何日前から作るのがいいの?」という質問、実はとても多いんです。
毎年のことなのに、忙しい年末にどう段取りを組むか、悩みますよね。
実は、おせち作りのベストタイミングは “3日前から”。
もっとも一般的なのは、12月29〜30日頃から作り始めるパターンです。
31日(大晦日)に仕上げると、元旦にちょうど食べごろになるんです。
ちなみに「29日は縁起が悪い」と聞いたことがある方も多いと思いますが、
最近では“苦労を重ねる=縁起がよい”という考え方も広まり、
あまり気にせず準備を始める家庭も増えています。
✅ ポイント:年末のキッチンは慌ただしくなりがち。
先に「火を使う料理」「冷まして保存する料理」を分けて考えると、ぐっとラクになりますよ!
おすすめの段取り(初心者でもムリなくできる3日スケジュール)
| 日付 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 12月28日ごろ | 黒豆・田作り・数の子など“日持ちするもの” | 砂糖や塩で味をしっかり付けると保存性がアップ。 |
| 12月30日 | 煮しめ・紅白なますなど“冷蔵で2〜3日もつ料理” | 酢や出汁の風味を整えて冷蔵庫へ。 |
| 12月31日 | 伊達巻・海老のうま煮・焼き物など“当日仕上げる系” | 食べる直前に作って香りと色を楽しむ! |
「年末ギリギリに全部やるのはムリ!」という方も、このスケジュールなら無理なく進められます。
“日持ちするものから順に作る”が、おせち成功の鉄則です。
おせちは何から作る?初心者でも失敗しない順番
初めておせちを作る方にとって、最大の悩みは「どれから作ればいいの?」ですよね。
実はおせちは、“日持ちの長い料理から作る”というだけで、驚くほどスムーズに仕上がります。
順番にコツを押さえていきましょう👇
① 黒豆・田作り・昆布巻き(保存性◎)
これらは砂糖や醤油をたっぷり使うため、5日ほど日持ちする定番料理。
甘辛く煮詰めることで、時間が経つほど味がなじんで美味しくなります。
黒豆は“まめに働けるように”、田作りは“豊作祈願”という意味もあり、
縁起的にも最初に取りかかるのにぴったりです。
💡ワンポイント
黒豆は前日から水に浸しておくと、皮がシワになりにくく、ツヤツヤに仕上がります!
② 紅白なます・酢れんこん(彩り担当&保存も効く)
おせちに華やかさを添えるのが、紅白なますと酢れんこん。
酢を使うことで殺菌効果があり、冷蔵で3日ほど日持ちします。
特に紅白なますは、紅白の色が「平和」や「お祝い」を意味するため、
見た目も美しく、お正月らしさを演出できます。
🥕ちょっとおしゃれにしたい人は…
柚子の皮を器にしたり、すだちを加えて香りをアップすると、
SNS映えする「おせち 手作り おしゃれ」な一品に早変わりです!
③ 筑前煮・煮しめ(家庭の味代表)
煮しめや筑前煮は、家庭によって味がまったく違う“個性派おせち”。
野菜の水分が多いため、冷蔵で2〜3日が目安です。
根菜類は火をしっかり通すことで、味が染み込みやすくなります。
年末にまとめて作り置きしておくと、正月三が日に温め直しても美味しいですよ。
🍲コツ
煮物は汁ごと保存すると乾燥しません。
食べる直前にもう一度温めると、味が蘇ります。
④ 伊達巻・海老のうま煮(できたてを楽しむ)
これらは大晦日に仕上げる系の料理。
ふんわり焼き上げた伊達巻や、色鮮やかな海老のうま煮は、冷蔵でも保存はできますが、やっぱり出来立てが一番です。
特に海老は火を通しすぎると固くなるので、大晦日に軽く煮ておくのがベスト。
食卓に並べるときに少し温めるだけで、艶やかに仕上がります。
🍳ワンポイント
伊達巻は“知恵を巻く”といわれる縁起料理。
卵焼き器がなくても、オーブンシートを使ってフライパンで焼けますよ!
おせちは「3日前」から作るのが理想!初心者でも失敗しない作り方と日持ちのコツ
おせちは何日前から作るのがいいのか迷う方も多いですよね。
実は、理想的なタイミングは「元旦の3日前」、つまり12月29〜30日頃から作り始めるのがポイントです。
ここでは、「おせちは何から作る?」「何日もつ?」「作り置きのコツ」などを、初心者にもわかりやすく解説します。
ここでは、おせち作りのタイミングから保存の工夫まで、年末を快適に過ごすヒントをまとめて紹介します。
おせちは「3日前」から準備するのがベスト
最も一般的なのは、12月29〜31日の3日間で仕上げるスケジュール。
29日は「苦労を重ねる日」として避ける方もいますが、最近では縁起を気にしない家庭も増えています。
31日に完成させて、元旦にちょうど食べごろになるようにするのが理想です。
おすすめの段取り
-
12月28日頃: 黒豆・田作り・数の子など「日持ちするもの」から
-
12月30日頃: 煮しめ・紅白なますなど「冷蔵で2〜3日もつ料理」
-
12月31日: 伊達巻・海老・焼き物など「当日に仕上げる料理」
この順番で進めると、無理なく準備でき、彩りも味も美しく仕上がります。
おせちは何から作る?初心者でも失敗しない順番
おせち作りのコツは、「日持ちが長いものから作る」こと。
料理ごとに保存期間を意識すれば、作り置きも安心です。
黒豆・田作り・昆布巻き:砂糖や醤油を使うため保存性が高く、約5日間日持ちします。
紅白なます・酢れんこん:酢の力で3日ほど保存可能。彩りも良く“おせち料理定番”の人気メニューです。
筑前煮・煮しめ:野菜の水分が多いため2〜3日が目安。汁ごと保存し、食べる前に温め直すのがおすすめ。
伊達巻・海老のうま煮:風味が落ちやすいため、大晦日か元旦に作るのがベストです。
冷蔵庫保存では、清潔な容器に詰め、ラップでしっかり乾燥を防ぐのがポイント。
「おせち 手作り おしゃれ」に仕上げたい方は、少量をきれいに盛り付けるだけでも印象が変わります。
「元旦に作る派」VS「作り置き派」それぞれの魅力
最近では、「元旦に作る」スタイルも人気です。
自分の暮らし方や冷蔵スペースに合わせて選んでOK。
🌸 元旦に作る派の特徴
-
温かい料理を食べたい
-
作りたての香りを楽しみたい
-
冷蔵庫がいっぱいで作り置きできない
そんな方に人気なのが、“ハーフおせち”スタイル。
黒豆や栗きんとんなどは市販品を使い、筑前煮や伊達巻などを元旦の朝に作ります。
白いプレートに少しずつ盛り付けた“モダンおせち”は、SNSでも「#おせち手作りおしゃれ」で話題!
見た目もおしゃれで、出来立ての香りが家族に大好評です。
🎍 元旦に作らない派(伝統派)の考え方
一方で、昔ながらの家庭では「元旦に火を使わない」という習わしも。
これは、“神様を迎える神聖な時間に炊事をしない”という意味があります。
おせちは本来「保存食」として作られた料理。
元旦に料理をしなくても、日持ちするよう設計されているんですね。
どちらが正解というわけではなく、「自分の暮らしに合うおせちの形」を選ぶことが大切です。
おせちはどれくらい日持ちする?理由と作り置きのコツ
おせちはもともと常温で3日ほど日持ちするよう考えられた料理です。
現代では冷蔵・冷凍保存ができるため、より長く安全に楽しめます。
おせちが日持ちする理由
-
砂糖・塩を多く使用(黒豆・田作り・栗きんとんなど)
-
酢や酒の抗菌効果(紅白なます・酢れんこんなど)
-
しっかり加熱して水分を飛ばす(焼き魚・伊達巻など)
これらの工夫が“菌の繁殖を防ぎ、味を長持ちさせる”秘訣です。
作り置き・保存のコツ
-
清潔な密閉容器で保存(乾燥・酸化を防止)
-
煮物は汁ごと保存し、食べる前に再加熱
-
冷凍できるもの(栗きんとん・黒豆)は小分け冷凍がおすすめ
「おせち 手作り 安く」仕上げたい方は、業務スーパー食材+自家製アレンジがコスパ抜群。
盛り付けを工夫すれば、“おせち 手作り おしゃれ”な仕上がりにもなります。
手作りが大変なときは“半手作り”でOK!
全部を一から作るのは大変……そんなときは、市販のおせち+手作り1〜2品の“半手作り”で十分です。
黒豆や数の子は通販・冷凍で購入し、筑前煮やなますだけ手作りする。
それだけでも、家庭の温かみを感じられる立派なおせちになります。
最近では、添加物控えめで自然派な「冷凍おせち」も多く、忙しい人や少人数家庭にも人気です。
まとめ|おせちは「3日前」から計画的に!無理せず楽しむのが一番
-
おせちは3日前(12月29〜31日)から作り始めるのが理想
-
「日持ちする料理」から順に作ると失敗しない
-
元旦に作るのもOK!ライフスタイルに合わせて選ぼう
ここでは、「おせちは何日前から作る?」という疑問を中心に、作り方・日持ち・保存のコツを紹介しました。
無理なく計画的に準備して、気持ちのいい新年を迎えてくださいね🎍
| 特徴 | 無添加・自然派食材中心。野菜たっぷりで健康志向。 |
|---|---|
| 味・見た目 | やさしい味、彩り控えめでナチュラル。 |
| 安心感 | 国産素材&自社製造で安全 |
| 特徴 | 料亭監修おせちの通販大手。顧客満足度94%以上。 |
|---|---|
| 味・見た目 | 華やかで豪華、家族向け。 |
| 安心感 | 有名料亭監修で信頼性抜群 |
| 特徴 | 創業55年の老舗。添加物不使用の冷凍惣菜で有名。 |
|---|---|
| 味・見た目 | 上品な味わい、冷凍でも高品質。 |
| 安心感 | 徹底した安全基準で安心 |